introduction
スタートアップの研究開発には、コストとスピードという二重の課題があります。これを解決する選択肢の1つが、「中古機器導入」。今回は、実験台や薬品庫などのラボの設備をCo-LABO MAKER経由でご購入いただいた実体験を伺います。金属の微細造形技術を扱うスタートアップ、3D Architechの工藤さんにお話を聞きました。
ラボ拡大でコスパ良く研究機器を揃えたい。解決の鍵は「ネットワーク」
—本日はよろしくお願いします。まずは、3D Architechで展開されている事業について教えてください。
私たち3D Architechは、金属の3次元での微細造形技術を専門としています。通常の金属粉末を使用したものとは違い、弊社では、非常に細かい構造を再現できるゲルベースの方式の3Dプリンティングに取り組んでいます。通常の3Dプリンターだと、高額なものは1台で1億円近くしますが、当社の方式だとプリンター自体は数万円から購入できるものもあり、初期導入コストが大幅に抑えられるんです。
—材料コストについても工夫されているとか。
その通りです。金属粉末は原材料として非常に高価ですが、当社の方式では金属粉末を使用しないため、材料コストも大幅に削減されています。つまりマシンと材料の両方で低コスト化が実現可能な技術です。
また、最近はこのミクロ構造を造形できるという弊社の技術を武器に、熱制御技術や水素関連技術にも取り組んでいます。
—そのように新規事業にも取り組まれていく中で、中古機器の導入を検討したきっかけは何だったのでしょうか?
ちょうど今、ラボを広げているタイミングなのですが、設備購入費がかなり重くのしかかってきたんです。たとえば実験台だけで100万円近くすることもあり…。安く購入できるもので、十分に使えるという保証があるものだったら、全然安いに越したことはないということで、以前から関係のあったCo-LABO MAKERさんのサービスを利用させていただきました。
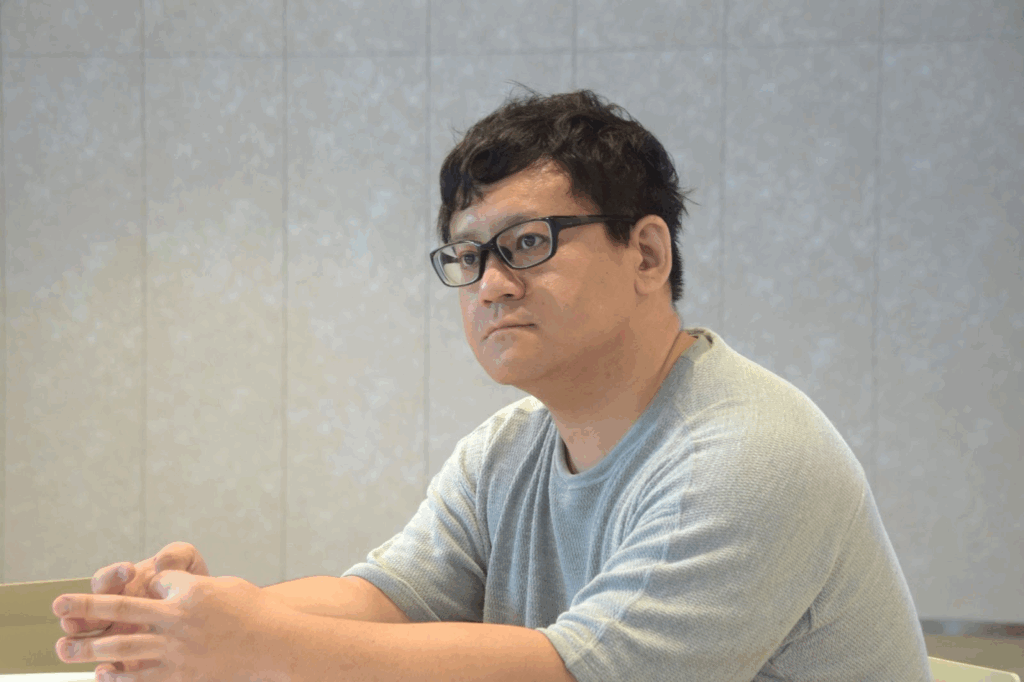
—Co-LABO MAKERのサービスを知ったきっかけは?
実はCo-LABO MAKER代表の古谷さんとは大学の同級生で、昔からお世話になっていました。もともと研究開発を支援する事業をしていることは知っていましたが、メルマガなどで中古機器の売買もしていることを知り、中古機器の導入を検討するにあたって相談したのがきっかけです。
スタートアップの研究開発では、こういうネットワークの力が大きいと実感しましたね。
—ネットワークが解決の鍵になったのですね。
そうですね。たとえば予算って、ちょうど消化したいタイミングに中途半端な量が余ったりするじゃないですか。使わなきゃならない期限があるけれども、買いたいものは予算が足りない、、というときに、「実は同じ性能のものがもっと安く買える」という情報が入手できたらとてもありがたいんですよ。こうやってうまく情報を入手できると、研究開発も無駄なくスムーズに進められて、結果的に研究成果にも直結すると思うので、幅広いネットワークを持っておくことは重要だと思いますね。
我々がこうやってインタビューを受けることも、何かのつながりのきっかけになれば嬉しいと思いますし、弊社に限らず、ネットワークはスタートアップにとって大きな武器になるのではないかと思っています。
中古機器はスタートアップ研究開発の強い味方になる。
—中古機器の性能や状態に対して、不安はありましたか?
今回は、精度が求められる設備ではなく、あくまで実験台や薬品庫といった基本設備が中心だったので、性能の不安はありませんでした。全て中古か全て新品かの2択ではなく、測定機器など精度が重要なものは新品で購入しつつ、求める性能が劣化しにくいタイプの機器は中古で購入するなど、バランスよく戦略を立てるといいと思いますね。
また、私は以前大学の研究室で研究をしていたのですが、そこでも古い機器を使う経験があったので、中古機器を使用すること自体にはあまり抵抗はなかったですね。
—実際に購入してみて、いかがでしたか?
値段相当以上の状態の良さでした。例えば冷蔵庫だと、前使用者の薬品の匂いや汚れがどのくらい残っているか心配だったのですが、全然そういうところもなかったし、物によってはかなり新品に近い状態のものもあったので、すごく満足しています。価格は大きく抑えられていながら、ここまで状態の良いものを購入することができて、とても良かったです。

—最後に、中古導入を検討するスタートアップへのメッセージをお願いします。
スタートアップの研究開発には、常にコストとスピードのバランスが求められます。特に、予算が限られ新品導入が難しいスタートアップでは、中古という選択肢はとても魅力的ではないでしょうか。
今後も必要な機器が出てくると思いますので、そのときはぜひCo-LABO MAKERさんに相談しつつ、中古という選択肢を活用していきたいですね。
—本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
